巷で広く認識されているであろう「体幹トレーニング」?
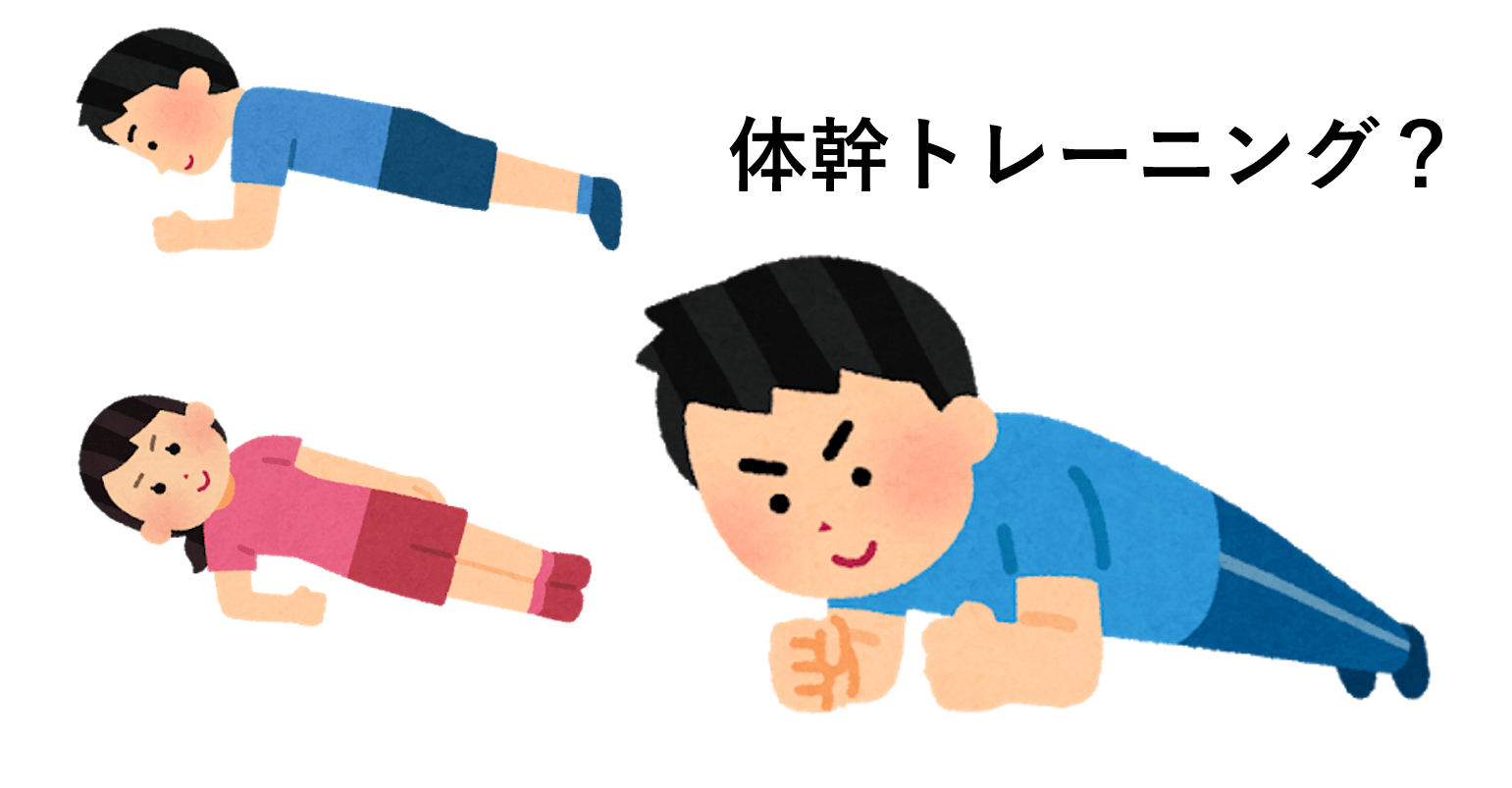
巷でよく知られるところの体幹トレーニングと言えばまずコレです。これはプランクと呼ばれるものです。背中からお尻まで一直線になるような姿勢を正しくキープする、そのための筋肉の協調性、安定性をチェックしたり、軽い刺激を入れたりするエクササイズです。別にこのエクササイズ自体を否定する訳ではありません。背中からお尻まで一直線になるような姿勢を正しくキープするための筋肉の協調性、安定性をチェックしたり、軽い刺激を入れたりする目的、その他諸々の目的ありきで実施する分には何の問題もありません。
ただ疑問を呈したいのは「この体幹トレーニングを行なっていれば、体幹がつよくなって、ブレない身体が手に入って、運動パフォーマンスが向上する」という認識です。
「プランク=体幹が強くなってパフォーマンスが上がる」という認識の問題点
強度がとても低い
まず、プランクのような自体重で姿勢をキープするようなエクササイズでは「体幹」と呼ばれる部位にそこまで大きな負荷がかかりません(ここでいう「体幹」とは、脊柱を支えてその位置を保つ筋群を指しています)。考えてみれば至極当然です。背中に数十キロのプレートが乗っている場合や、運動習慣が無く身体全体の運動機能が著しく低下している方が実施しているのならまだ納得できる部分があります。しかし、爆発的なパワーを発揮したり、日々何キロもランニングを行うアスリートにとって、これが体幹のブレを防いでパフォーマンスを大きく向上させるに足るトレーニング刺激となり得るかと言われると、さすがに首をかしげざるを得ません。
実際に、このフロントプランクにおける腹直筋の活動量は、最大収縮力の約20%ほどだと言われています(Aspe & Swinton,2014)。マックスの5分の1程度の筋力で、全身をフルに使う全力疾走、爆発的な跳躍運動、投てき運動での負荷に耐えうる「体幹」を十分に強化することができると言えるでしょうか?また、姿勢をピタッとキープするような単純な運動だけでその体幹とやらは十分に鍛えられるのでしょうか?
辛い=効果が高いではない
プランクを2分間ほど耐久しながらプルプル震えて、「めちゃめちゃ効いてる!強くなってる!」というコメントを残してトレーニングルーム去っていく人がいます。他のベーシックなウエイトトレーニングがしっかりとやれていれば、それは本人の達成感や爽快感だけの問題なので特に言及することはありませんが、問題視すべきは「プルプル耐久体幹トレーニング」に、大切なトレーニングのほとんどの時間を費やしてしまっている場合です。
「辛いし効いてる感じがある」のは間違いないでしょう。実際に筆者も2分プランクやれば悲鳴を上げます。しかし、一定の姿勢を長時間キープできる能力は、スポーツのパフォーマンスを向上させるためにそこまで重要なことなのでしょうか?フロントプランク耐久選手権なる競技会があるのであればまた話は別ですが、多くの場合スポーツのパフォーマンスを向上させるのに必要な体幹の能力というのは、低い出力で姿勢を長時間キープできる能力ではないはずです。
また、その運動で鍛えられているのは筋力というより持久力であり、それが何かパフォーマンスにつながる重要な能力の土台になるとも考え難いでしょう。
じゃあプランクって何?何でみんなやってるの?
「みんなやってるってことは、体幹(プランク)って重要なんじゃないの?」と言われたとします。確かにみんなやっているトレーニングは重要である可能性は高いかもしれません。それだけ効果を実感しているはずなんでしょうから。じゃあ何でこんなにスポーツのトレーニング現場でプランクがなされているのか?
これに対して一言、「すみません。よく分かりません。」(Hey Siri)
どうしてこんなにもみんな好き好んでプランクをやりたがるのかが、この記事を書いている筆者にも全く分かりません。とある有名人やメディアによって形だけが広まって、そのまま収集が付かなくなってしまっているのかもしれません。確かに、トップアスリートや有名なメディアが取り上げるトレーニングは、効果がありそう、強くなれそうだと感じてしまいやすいものです。
加えてこの「体幹」というワードは曲者で、その意味合いが非常に抽象的で、誰にとっても受け入れられやすい(直感的に効果が高そうだと認識してしまう)側面を持っているように感じられます。例えば、次のようなパターンです。
①メディア:「トップアスリートは体幹がブレない(トップアスリートの動画を挿入)」
②視聴者:「本当だ、トップアスリートは体幹がブレてない!」
③メディア:「トップアスリートはこんなエクササイズをしていた!(トップアスリートがやや難易度が高いプランクをしている動画を挿入)」
④メディア:「体幹が弱い人はブレるので、これができません(運動習慣の無いタレントがエクササイズを模倣し、失敗)」
⑤メディア:「これがトップアスリートの強さの秘訣。体幹をトレーニングが大事です!」
⑥視聴者:「なるほど。体幹(プランク)が大事なんだ。」
「あるエクササイズで姿勢をブラさずにキープできるorできない人の光景」と、「競技パフォーマンス中のブレない体幹のイメージ」は、トレーニングについてあまり考えたことのない人々にとって非常にリンクしやすいものです。
直感的にその重要性を誤認してしまうのも無理はありません。また、ここでいう「体幹」とは具体的に何を指しているのかを考える視聴者なんて数%も存在しません。「体幹」と言われれば「ああなるほど体幹の強さかぁ」以上のことを一般の方々は考えないのが普通です。少なくとも私の母は考えません。
ある有名アスリートやメディアの影響力は非常に大きいものです。「体幹トレーニング」の言葉の一人歩きもこのようなところから発展したものなのかもしれません。そして、いつの時代も、その言葉の意味や目的が取り除かれて形骸化してしまった「流行りのトレーニング」が絶えることは無いと考えられます。「タピオカの次は何が来るだろう・・・」と考えるのと同じように、「体幹」や「タバタ」の次は何が来るだろう…と考えるのが私の習慣になっています。